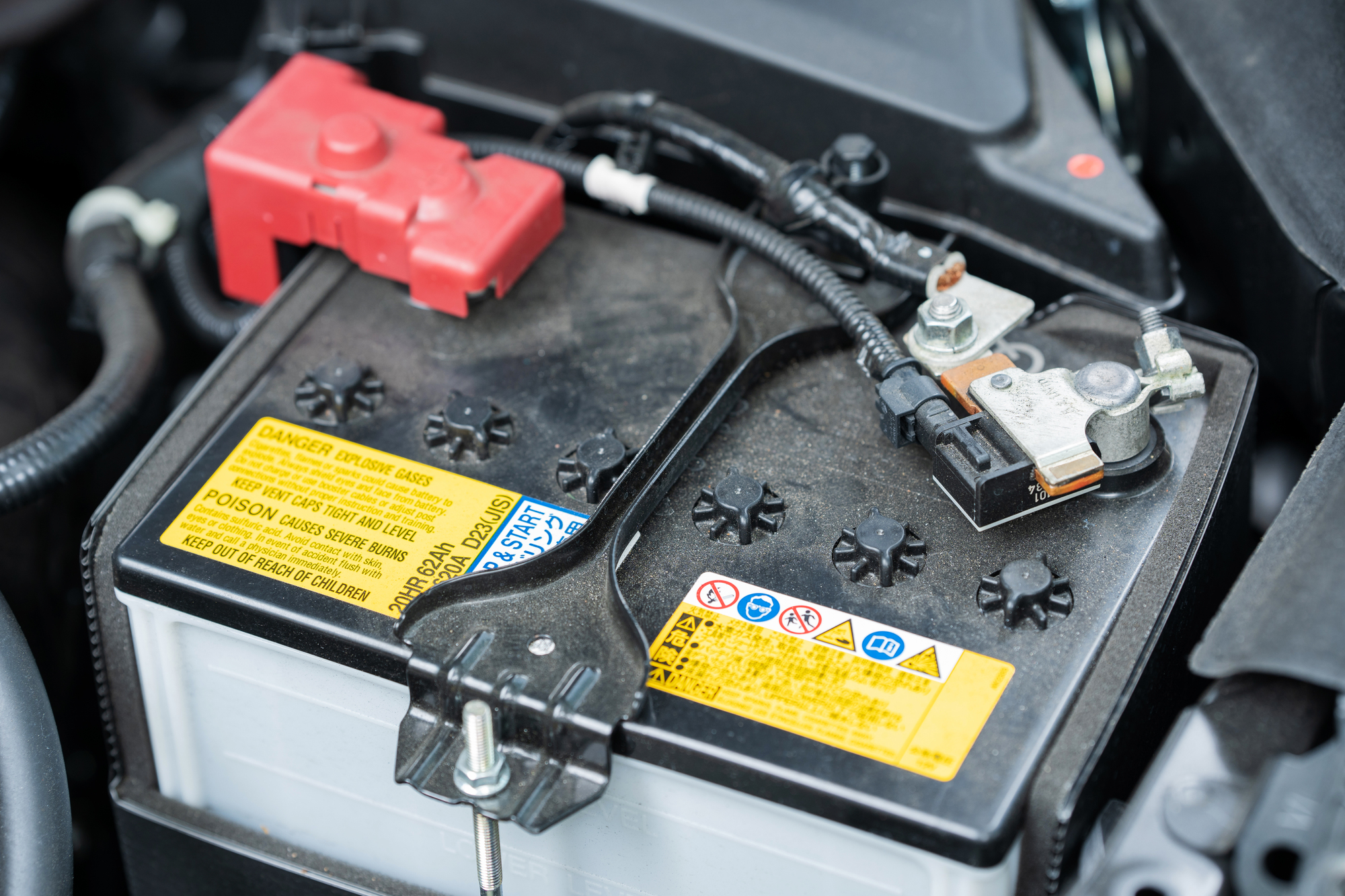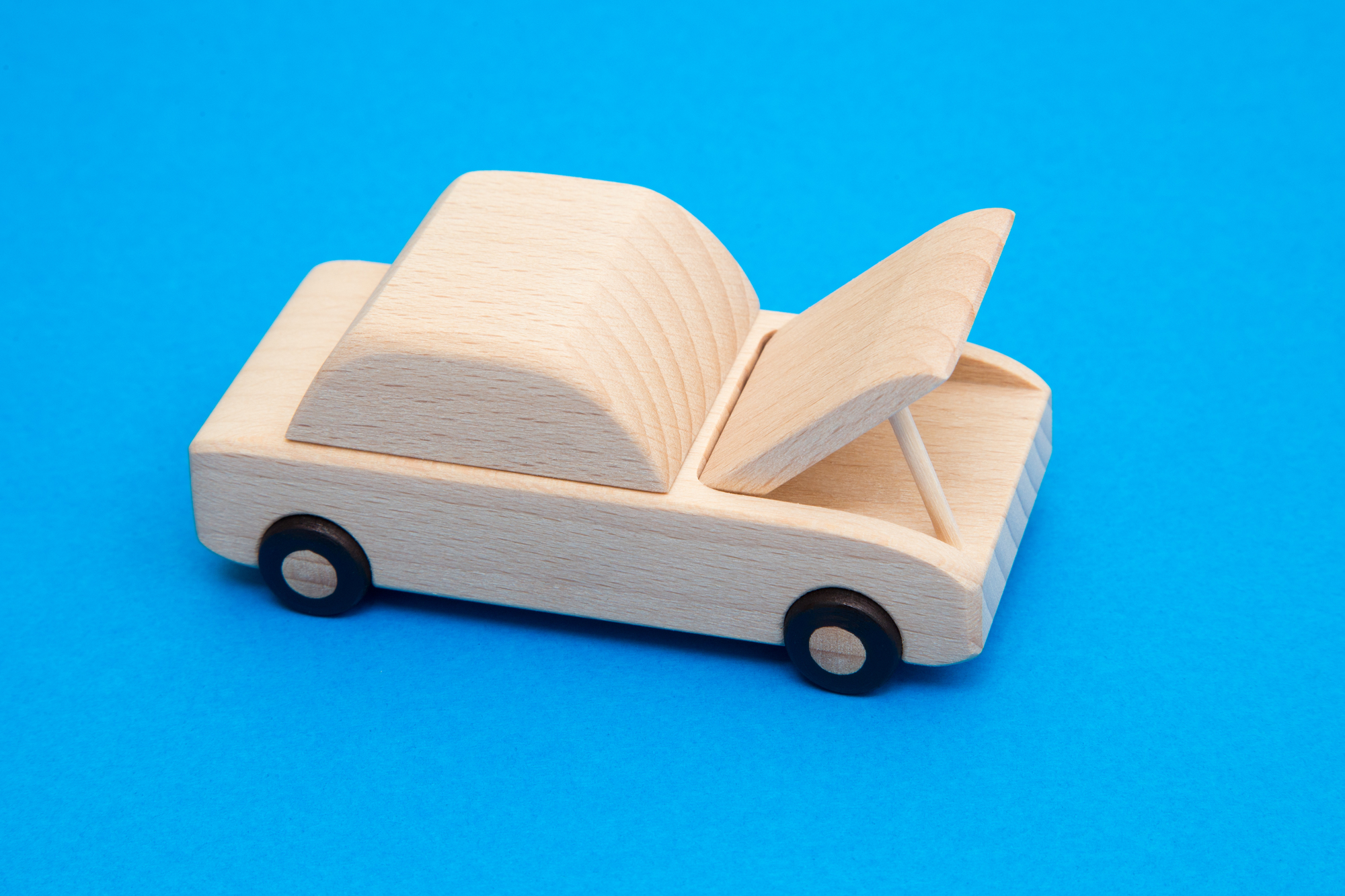工場・建設業界で欠かせない存在である「クレーン車」クレーン車を用いた仕事は平均年収が400~500万以上稼げるケースもあり、需要が高いです。
そんなクレーン運転士になるにはどのような免許・資格が必要になるのか?具体的にご紹介いたします。
■クレーン免許の種類
クレーンは取得する免許によって、運転できる機体も異なってきます。ここで、代表的なクレーン免許について解説していきます。
・クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
クレーンとデリック、両方の機種を扱うために必要になる免許です。デリックとはマスト・ブームを有した機械装置で、動力によって、荷を吊り上げることができます。(吊り上げ荷重0.5t以上のもの)
・クレーンとデリックの違い
クレーンは単体で荷の吊り上げが可能ですが、デリックの場合は、設置されているワイヤーロープやブームの操作を別の原動機で操作します。ビル建設や製鉄所など、活躍できる範囲が広いので、持っておくと便利です。
・クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
クレーン限定はデリックを除いた吊り上げ荷重が5t以上のクレーンを運転することができる免許です。クレーン初心者の方で、少し重量の大きいクレーンを運転したいという場合は、まずこの免許を取得してみてはいかがでしょうか。
・床上運転式クレーン限定免許
床上運転式クレーンは工場内部の天井に設置されている、吊り上げ荷重が5t以上のクレーンです。UFOキャッチャーの要領で、工場内の荷物を運び、運転手は運ばれている荷の移動と一緒にボタンを操作します。床上式運転は操縦者の少ない移動で運転することができるので、玉掛け業務の際に便利になる資格です。
■クレーンの運転に必要な資格や免許
クレーンは、工場などで使用する定所式、自走できる移動式、デリックの3種類に大別できます。運転をするクレーンに応じて、免許を取得しましょう。
・クレーン(定所式)の運転に必要な免許や資格
<吊り上げ荷重5t以上>
クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
<吊り上げ荷重5t以上の床上運転式>
クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
<吊り上げ荷重5t以上の床上操作式>
床上操作式クレーン運転技能講習
<吊り上げ荷重5t以上の跨線テルハ>
クレーンの運転の業務特別教育
<吊り上げ荷重5t未満>
クレーンの運転の業務特別教育
・移動式クレーンの運転に必要な免許や資格

<吊り上げ荷重5t以上>
移動式クレーン運転士免許
<吊り上げ荷重1t以上5t未満>
小型移動式クレーン運転技能講習
<吊り上げ荷重1t未満>
移動式クレーンの運転の業務特別教育
・デリックの運転に必要な免許や資格
<吊り上げ荷重5t以上>
クレーン・デリック運転士免許
<吊り上げ荷重5t未満>
デリックの運転の業務特別教育
現在、ご紹介した免許のみではクレーン業務に必要な玉掛け作業が行えません。
吊り上げ荷重1t以上の場合は玉掛け技能講習、1t未満の場合は玉掛け業務の特別教育の資格が必要です。
※昭和53年9月30日以前に免許を取得した場合は可能です。
■技能講習が必要なクレーンの免許は?
クレーンの操作に関する免許には種類があり、どれを取得するかで操作できるクレーンの種類が異なります。こちらでは、技能講習が必須になる免許をご紹介いたします。
・小型移動式クレーン
吊り上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンのことを小型移動式クレーンと呼びます。技能講習には学科と実技があり、受講後には試験が行われます。試験に通らなければ免許を取得することはできません。
クレーンの免許の中では比較的取得しやすい難易度ですが、応募者が多いため余裕をもって応募しておくようにしましょう。
受講費用は3万円ほどです。
・床上操作式クレーン
移動式クレーンとは異なり、クレーンが工場の天井などに設置されています。吊り上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンを運転するには技能講習が必須です。操作はペンダントスイッチで行います。
床上操作式クレーンで注意したいのが、荷物の積み下ろし作業には玉掛の免許も必要になるという点です。床上操作式クレーンの免許を取得する場合は玉掛の免許も取得しておきましょう。
費用は2万~3万円程度です。
・1トン以上の玉掛け
クレーンのフックに荷物を掛ける作業や、降ろす作業に必要な免許です。クレーン作業には必須の免許なので、先に取得しておくことをおすすめします。
講習には2日間の学科と1日の実技があります。
費用は所持している資格や免許によって変動しますが、およそ2万2,000円程度です。
■合宿なら費用を抑えて短期間での取得が可能
できるだけ短期間で取得を目指す場合は、合宿での取得を考えてみることもおすすめです。
こちらでは合宿でクレーンの免許を取得する方法や、知っておきたい費用を抑える方法についてご紹介いたします。
・合宿の費用を抑える方法
クレーンの免許を取得したい場合に確認しておきたいのが、「教育訓練給付金制度」です。これは厚生労働省が実施している助成金制度で、条件に当てはまれば免許取得に必要な費用の20%(最大10万円)が支給されます。支給申請をする場所はハローワークですので、興味がある方は一度調べてみることをおすすめします。
・合宿に必要な期間と費用
こちらはあくまでも目安になりますが、合宿で免許取得にかかる費用と期間をご紹介いたします。
なお、紹介している費用は受講料金とテキスト代のみです。宿泊費用や保険料は別途必要となりますのでご注意ください。
<移動式小型クレーン>
費用…4万2,000~4万5,000円程度
期間…3日間(学科10~13時間 実技6~7時間)
※有する資格によって異なる
<床上操作式クレーン>
費用…4万2,000~4万5,000円程度
期間…3日間(学科10~13時間 実技6~7時間)
※有する資格によって異なる
<玉掛技能講習>
費用…2万~2万5,000円程度
期間…3日間(学科9~12時間 実技6~7時間)
※有する資格によって異なる
宿泊費用は滞在する部屋のグレードや教習先によって異なりますので、受講する教習先のホームページなどで確認してください。
■クレーンの免許を取得するメリット
クレーンの免許を取得することで大きなメリットがあります。
・安定した収入が見込める
クレーン運転士を目指す場合はもちろん、安定した収入を求める方にもクレーン運転士の仕事はおすすめです。国家資格であり、高い専門技術が必要なため、非常に需要が高く就職にも有利になります。
免許に期限がないため、一度取得すれば使い続けることができます。
・性別に関係なく給与やスキルのアップが可能
あるデータによると、クレーン運転士の収入は平均で460万円程度とされています。男女別で見ても、男性が460万円、女性が450万円となっており、性別に関係なく高収入の仕事といえます。
スキルアップや再就職にも性別問わず有利になれるため、取っておいて損はない免許です。
また、年代別では20代前半で約400万円、30代前半で約510万円、40代前半で約530万円、50代前半で約540万円と、地域や経験、スキルによる差は少ないようです。
実務経験があるに越したことはありませんが、未経験でも高い収入が見込めるでしょう。
すでにクレーン運転士の免許を取得している方は、より高い収入を目指して、港湾などで使用されているガントリークレーンの運転士免許を取得するのもよいかもしれません。
ガントリークレーンの免許は数日で取得できるので、スキルアップも兼ねてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
■クレーン免許が役に立つ現場
クレーンが使用されているのは、建設現場だけではありません。
・クレーン運転士という仕事
クレーンは工場、製造所、倉庫、港湾、その他にも多くの現場で活躍しています。そのため、運転士免許を保有していると、全国どの地域の現場でも重宝されるでしょう。
ただし、危険性の高い作業を行う前はしっかりと計画を立て、運転中に事故が起きないよう入念に打ち合わせをするなど、責任能力や管理能力、周囲への配慮が必要です。
また、クレーンは大きなものを運ぶイメージばかり先行していますが、繊細な作業も多く、ストイックさが求められる仕事です。体や心の不調は仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすため、規律正しい生活とともに自己管理を徹底する意識も求められます。
・クレーン運転士のやりがい
無事に計画通りの作業を終えた際は、大きな達成感と安堵感、やりがいを感じられるでしょう。作業にはスピードだけでなく、慎重さや丁寧さも必要です。そのため、集中力や忍耐力、責任感の強い方が向いています。
周囲からの期待が大きいだけに、誇りをもって長く続けられる仕事です。
またクレーンは種類が多く、作業は奥が深いので、クレーン運転士の免許を独学で取得するのは難しいと言われています。
続いてクレーン運転士の試験についてご案内いたします。
■クレーン運転士の試験について
クレーン免許を取得したい場合は、教習所に通うのがおすすめです。教習所に通うと実技試験が免除になるので、免許取得率もぐんと高くなりますし、時間の節約にもなります。
ここで、教習所での試験内容について、より詳しくご紹介いたします。(クレーンデリックの運転免許は18歳以上の方なら誰でも取得できます。)
・主な試験内容
試験内容については、クレーン・デリックに関する知識、原動機に関する知識、クレーンの運転に必要な力学知識、法令などの知識が主な出題内容になります。学科試験は総得点で満点中60%以上の高得点。各科目が40%以上の得点率であることが必須になります。期間としては大体7~10日ほどです。
・試験難易度
クレーン免許の取得となると、難しいイメージがありますが、教習所に通うと、実技試験が免除されるので、難易度的には心配するほど高くありません。教習所に通いたくない方は独学で一発試験を狙う方法もありますが、その場合、実技試験を受けることになり、クレーン操縦経験のある方でないと、かなり合格が難しくなってしまいます。時間はかかりますが、教習所でじっくり講習を受けたほうが確実といえるでしょう。
・平均的な合格率
クレーン免許の合格率は、年によって違いはありますが、学科試験の場合は約61%、実技試験の場合は約48%の方が合格という調査結果が出ています。実技試験の場合は、やはり合格率は若干下がるようです。
■中古クレーンを購入する際の注意点
クレーンは新車で購入するとなると、かなりの出費になるので、中古購入したいという方も多いと思います。中古トラックは通常より安く手に入れられる反面、安全性の確認を怠ると、後々、事故を起こしてしまう危険があるので、注意しましょう。ここで、中古クレーンを購入する場合に大切なポイントをご紹介いたします。
・クレーンは問題なく稼働するか
基本的ですが、最も大切な問題です。ただ動くかどうかだけでなく、諸動作が滑らかに操作できるか、止めたいタイミングで確実に停止させることができるかなどに、気を付けて確認しましょう。作業時にタイムラグが発生していないか。エンジンの回転数を上げた場合と通常時の動きの動作確認、エンジンのアイドリング確認なども重要なポイントです。
・補強板の有無
フレーム(シャーシ)を固定する補強板は、クレーン車の強度・耐久性を保証する上で重要な要素です。中古車のなかには、補強板がただの鉄板を加工して取り付けられたものもあるので、注意しましょう。鉄板の場合だと、シャーシがダメージを受けて曲がってしまったり、真っ二つに折れてしまう可能性があり、とても危険です。シャーシがダメージを受けると、業務用車両の安全性を根本から失ってしまうため、補強板の確認は必須です。
・点検整備記録簿
クレーン車のような業務用車両を選ばれる際は、点検整備記録簿の内容はしっかり確認しておきましょう。点検整備記録簿は車検以外で3ヶ月、6ヶ月毎に行う点検整備の記録を記帳し、保管しているものです。こうした点検記録は車両の安全性を確認するうえで大切なものです。販売開始日から使い込まれていない中古クレーンは、軽整備のみの場合もありますが、一通り目を通しておくといいでしょう。